「マンションの大規模修繕で出てきた見積、これって高すぎない?」「なぜこの工事項目が必要なのか、住民の誰も説明できない…」
──そんな不安や疑問を、管理組合の理事の方や修繕委員会の方々からよく耳にします。
大規模修繕は、マンションの将来を左右する一大プロジェクトです。その費用は数千万円、時には億単位にものぼり、区分所有者全員が負担する大きな支出となります。にもかかわらず、多くの現場では「専門的すぎてよく分からない」「設計事務所や管理会社に任せるしかない」と、消化不良のまま意思決定が進んでしまうことも少なくありません。
弊社でも大規模修繕工事に関わる際は、管理組合様・修繕委員会様と打ち合わせをする機会が多くありますが、建物について詳しい方がいる場合は稀です。
基本的には知識のない方でも分かるような資料を用意し、順序立てて丁寧に説明することを心がけております。
しかしながら、工事に関わる数ヶ月〜1年程度で、工事業者の説明を完全に理解し、必要に応じて指摘や意見を出すのはかなり難しいことと思います。
こうした中で注目されているのが、“セカンドオピニオン”という考え方です。
医療の世界では当たり前となったセカンドオピニオン──つまり、主治医以外の第三者に意見を求めること。それを建築の世界に応用することで、「見積の妥当性」や「工事内容の適切さ」を客観的にチェックできる手段が生まれました。
この記事では、なぜ今「大規模修繕にセカンドオピニオンが必要とされているのか」、そしてどんな効果が得られるのかを、一級建築士の視点から詳しく解説します。
なぜ“セカンドオピニオン”が大規模修繕に必要なのか

「そもそもセカンドオピニオンって本当に必要なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。しかし、実は大規模修繕こそ、“もう一つの視点”が求められる場面なのです。その理由は主に3つあります。
1. 大規模修繕は“高額で専門的”なプロジェクト
マンションの大規模修繕は、一般的な戸建て住宅のリフォームとは桁違いのスケールです。外壁の補修、防水工事、給排水管の更新、共用部分のリニューアル──数十年先を見据えた工事計画には、専門性の高い知識と判断が必要です。
さらに、金額は数千万〜億単位。にもかかわらず、住民のほとんどが「内容を正確に理解できていない」というのが現実です。
2. 設計事務所や管理会社に“完全にお任せ”でいいのか?
設計事務所や管理会社が作成した見積や工事内容を、そのまま鵜呑みにしていませんか?もちろん、信頼できるパートナーであることが前提ですが、その提案が本当に「中立的」で「住民の利益に適うもの」かを見極める必要があります。
なぜなら、一部の業者は特定の施工会社と繋がっていたり、入札の形だけを整えて高額な業者が選ばれるケースもあるからです。つまり「透明性が見えづらい構造」になりやすいのが大規模修繕なのです。
近年問題になった大規模修繕工事による設計事務所・管理組合・施工会社による談合については、こちらの記事でも説明しております。
3. 決断の責任は、理事会・組合にある
最終的に「この見積で進める」「この業者で契約する」と決定するのは、理事会や総会です。だからこそ、一時的でも“住民の立場に立った第三者の目”を加えることが、責任ある判断を支える道になります。
セカンドオピニオンは、「施工しない・利害関係を持たない」立場の専門家が、住民側に寄り添ってアドバイスを行うという新しいアプローチです。高額で不透明になりがちな大規模修繕のプロセスに、一石を投じる手段となるのです。
セカンドオピニオンとは?──「第三者の専門家」による見積・内容のチェック

建築における「セカンドオピニオン」とは、見積書・設計図・仕様書などの内容が妥当かどうかを、第三者の専門家が中立的な立場からチェックするサービスです。
このとき重要なのは、「当該工事や当該建物に関わっている施工業者でも設計事務所でもない」「直接の利害関係を持たない専門家」であること。A.t.oathにご依頼いただく際は、こうした条件を満たす一級建築士が対応します。
1. 工事の妥当性をプロが精査
大規模修繕の見積には、「この単価は適正か?」「数量が過剰ではないか?」「必要な工事とそうでないものが混在していないか?」といった疑問がつきものです。
セカンドオピニオンでは、数量の積算根拠や工事範囲の妥当性を細かくチェック。たとえば、「タイル補修が全体面積の50%になっているが、実際の劣化状況から見て適正か?」といった分析を行います。
2. コスト構成の中身まで検証
工事費は、材料費・人件費・仮設費・共通仮設費・現場管理費などの複合構成で成り立っています。ところが、見積の内訳が一式表記になっていたり、「諸経費」の中身が不明瞭なケースもあります。
セカンドオピニオンでは、これらを分解して「どこにコストが偏っているのか」「削減の余地がある項目はどこか」を明確にします。
3. 理事会や総会での“説明力”を補強
理事や修繕委員の方々が、住民に対して見積内容や工事の必要性を説明する場面は多々あります。その際、「プロの意見として第三者がこう評価しています」という後ろ盾があることで、合意形成や総会決議をスムーズに進められるというメリットもあります。
つまり、セカンドオピニオンは“見積が高いか安いか”を判断するだけでなく、“その工事が必要かどうか”までを住民の視点で一緒に考えてくれる存在なのです。
セカンドオピニオンを導入するタイミング

「セカンドオピニオンが有効なのは分かったけれど、いつ相談すればいいのか分からない」というご質問も多くいただきます。実は、導入のタイミングによって得られる効果が大きく変わるのがセカンドオピニオンの特徴です。
以下の3つのタイミングが、特に有効とされています。
1. 修繕設計前の段階
最も理想的なのは、まだ修繕内容が固まっていない「初期段階」での相談です。たとえば、「どこまでの範囲を工事対象とするか」「今やるべき工事・先送りでもよい工事の見極め」などを、設計段階で住民目線の整理ができるからです。
この段階でセカンドオピニオンを入れることで、過剰な工事や不要な設計コストの削減が見込めます。
また、大規模修繕工事の時期と関係なくご依頼をいただくこともございます。「いつも依頼している建築士事務所の見解を判断してほしい」「長期修繕計画の見直しが必要かどうかの判断をしてほしい」といったご依頼から関わらせていただくことで、将来的な修繕積立金の計画にも役立ちます。
2. 工事の仕様書・見積が出そろった段階
実際にセカンドオピニオンの依頼が多いのがこのフェーズです。設計事務所から出された見積書や設計仕様書をもとに、「この内容は適切か?」「高すぎる部分はないか?」を第三者の目でチェックしてもらいます。
複数社からの見積比較(相見積もり)をしている場合でも、見積の項目ごとに内容を読み解く知識がなければ、単純な価格比較では判断できません。専門家が見れば、「A社は安く見えるが、肝心の○○工事が含まれていない」などの見落としも明らかになります。
3. 施工会社決定の前
入札や見積の精査を経て、施工会社を決定する直前も重要なタイミングです。ここでは、選定プロセスが公正かどうか、価格が妥当か、施工体制に問題がないかを見極めます。
このタイミングでセカンドオピニオンを入れることで、将来のトラブル(追加費用の発生、工事の質への不満)を未然に防ぐことができます。
実例で見る、セカンドオピニオンの効果

「セカンドオピニオンって本当に効果あるの?」──そう疑問に思われる方のために、実際にA.t.oathが関わったセカンドオピニオンによる改善事例をいくつかご紹介します(内容は一部改変・匿名化しています)。
事例①:1,200万円の見積が950万円に削減
ある地方都市の中規模マンション(築28年)では、外壁補修・防水工事などの見積が1,200万円で提示されていました。理事会の方が「金額が想定よりも高い」と感じ、A.t.oathにご相談。
当社の建築士が見積書と劣化調査報告書を分析した結果、以下のような問題点が判明:
- 外壁補修の面積が劣化状況に対して過剰
- 仮設費(足場費用)が重複計上されていた
- 共通仮設・現場管理費が15%以上と高すぎ
これらを基に再見積を依頼したところ、約250万円のコストダウンが実現しました。品質を下げることなく、適正価格への是正ができた好例です。
事例②:「諸経費10%」の中身を開示 → 3%削減に成功
都内の分譲マンションでは、諸経費として10%が一括で計上されていました。しかし内訳の提示がないため、管理組合としては納得できず、A.t.oathにセカンドオピニオンを依頼。
調査の結果、以下の項目が“二重計上”になっていることが判明:
- 共通仮設費(足場・仮囲い)が別途記載されているにも関わらず、諸経費にも仮設関連費が含まれていた
- 監督員の常駐費用が、現場管理費と重複
これにより、諸経費を7%まで減額し、全体で数十万円のコスト圧縮に成功しました。
事例③:見積金額は変わらず、“安心感”を得られた
一方で、「結果的に大きな減額はなかったけれど、専門家の第三者評価が得られて安心した」というケースも多くあります。
特に、高経年マンションで住民の不安が高まっている場合、「プロが内容を確認して問題なしと言ってくれた」こと自体が大きな意味を持ちます。
セカンドオピニオンは削減だけが目的ではなく、“納得して進められる材料”を得るためのプロセスでもあるのです。
A.t.oathのセカンドオピニオンサービスの特徴
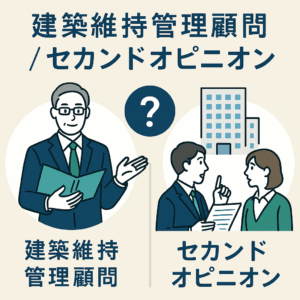
セカンドオピニオンサービスはさまざまな団体・建築士が提供していますが、A.t.oathでは「施工を請け負わない立場」だからこそ実現できる、中立性と専門性にこだわった支援を行っています。
1. 一級建築士による“実務視点”のチェック
私たちA.t.oathの建築士は、設計だけでなく、現場での施工管理・品質管理・原価管理の経験も有しています。そのため、「理想論」ではなく「現実的に意味のある」提案が可能です。
たとえば、「単価が高いように見えても、特殊な仮設条件によるものであればやむを得ない」といった判断を、現場を知る立場から客観的に助言します。
2. 完全中立の立場で対応
A.t.oathは施工業者ではありません。工事を受注することが目的ではないため、提案内容にバイアスがかかることはありません。また、特定の業者との資本関係・紹介関係も一切なく、住民・理事会の立場に立った支援を行います。
セカンドオピニオンの本質は、「誰のための助言か」が明確であること。A.t.oathではマンションの管理組合・区分所有者の利益最優先を原則としています。
3. 柔軟な対応とスピード感
「急に理事会で説明が必要になった」「見積の提出期限が迫っている」など、現場のスケジュールはタイトです。A.t.oathでは、1件から対応可能で、オンライン・郵送など多様な方法で迅速に対応いたします。
また、チェックレポートは専門用語を避け、理事会・総会でも説明しやすい形式でお渡ししています。
料金体系も明確で、事前にお見積りを提示。「依頼してみたら高額だった…」という心配もありません。
まとめ──迷ったら“第三者の目”を
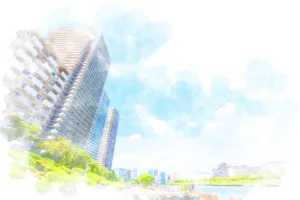
大規模修繕は、住民全員が費用を負担し、建物の未来に関わる非常に大切なプロジェクトです。
しかしながら、その意思決定の現場では、「専門的すぎて分からない」「業者に言われるがまま進んでしまう」といった状況が今もなお多く見られます。
だからこそ、中立的な第三者による“セカンドオピニオン”が重要です。
それは、見積の金額を下げるためだけではありません。内容に納得し、住民としての責任ある判断を下すための「情報の透明化」こそが、セカンドオピニオンの本質です。
A.t.oathでは、施工を請け負わない立場の一級建築士が、住民側に立ったアドバイスを提供しています。
- 「見積が高すぎる気がする…」
- 「管理会社や設計者の説明が曖昧で不安」
- 「理事会で専門的な根拠を示したい」
──そんなときこそ、私たちにご相談ください。
見積の読み解きから、住民説明の補助まで、プロの知見を“味方”にしませんか?
▶️ 無料相談はこちらから(URL:https://second-opinion.atoath.co.jp/)
📞 お電話でのお問い合わせ:03-5948-4756(平日9:00〜18:00)
株式会社A.t.oath(エーティーオース)について
建物とともに、人生も変わっていくからこそ。
マンションを買う。理事になる。
誰かに貸す。住み替える。
そのどれもが、あなたの人生にとって大きな転機です。
私たちA.t.oathは、そのすべてのシーンで「一緒に考えてくれる存在」であり続けたい。
不動産 × 設計 × 工事 × 点検
すべてのプロフェッショナルが揃った、住まいのリーディングカンパニーとして、
あなたのそばにいます。

株式会社A.t.oathホームページ https://atoath.co.jp/
見積査定サービス https://mitsumori-satei.atoath.co.jp/
建物維持修繕顧問 / セカンドオピニオン制度 https://second-opinion.atoath.co.jp/
